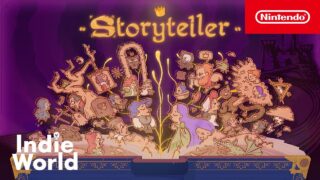許せるイライラを凌駕する許せないイライラ
はじめに
『人喰いの大鷲トリコ』を遊び終わって
トリコの虜()
ゲームにはプレイヤーを様々な形でサポートしてくれるNPCが存在する。薬草を売ってくれるおじさん、ルールを説明するロボット、プレイヤーを振り回すサマルトリアの王子。『人喰いの大鷲トリコ』でトリともネコともつかない、ティラノサウルスのようなサイズ感の奇妙な生き物との冒険を終えた今、僕はすっかり犬や猫を飼いたくなってしまうほどにトリコのことが気に入ってしまった。まったくお前は可愛すぎるゾ。
もう一度遊びたいとは思わないけど
先に言ってしまうと、『トリコ』はいいゲームだと思うが、リプレイアビリティは決してたかくない。それはゲーム側で周回プレイをサポートする機能がほとんど用意されてないこととは無関係だ。繰り返し遊べることが、必ずしも良いゲームの条件でないことはわかっているけれど、少なくとも『トリコ』は、相棒との再開を躊躇してしまうほどに、ゲームプレイにフラストレーションが溜まる要素が多かったように思う。
『人喰いの大鷲トリコ』とは?
『人喰いの大鷲トリコ』は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントより2016年12月6日に発売されたPlayStation 4用ゲームソフトだ。開発はSIEジャパンスタジオとジェン・デザイン。過去『ICO』(2001年 PS2)『ワンダと巨像』(2005年 PS2)を手掛けた上田文人さんがディレクターを務めた3作目だ。大鷲の巣と呼ばれる遺跡で目覚めた少年が、巨大な獣トリコと出会い、協力して遺跡からの脱出を目指す物語だ。かつてあった文明が滅びた(と思わせるような)未知の古代遺跡の中、ほぼ孤立無援の状態でさまよっていくゲーム体験は、上田作品に通じる世界観だ。
本記事のネタバレについて
本作はバイオハザードシリーズのようにゲーム内ドキュメントでストーリーを補足する要素がまったくなく、非常にミニマルな作りだ。また、僕自身が少ない情報から全体を考察できるほどに頭が良くないこともあり、ストーリーの展開やその良し悪しについて、本記事ではほぼ触れていないと思う。しかし、本作は謎解き要素があり、その解法について明確に触れている箇所があるので気をつけてほしい。
かわいいは正義
とにかくトリコがかわいいに尽きる
アニメーションがすばらしい
トリコの仕草は非常に自然だ。さすがに約十数時間のプレイ時間を共に過ごしていればパターンはいくつか見えてしまうが、それでも他の追随を許さないほどにトリコのアニメーションは上質だと断言できる。ゲームのアニメーションでよくあるのは、例えばあるスイッチの前で決定ボタンを押すと、スイッチを押すアニメーションが自然に再生できる立ち位置にスーッとスライド移動したり瞬間移動する現象だ。トリコはできる限り自然な動きの流れで(あるいは不自然な動作にプレイヤーが気づきにくいように)必要な地点に移動してくれる。ゲームクリアまでのあいだトリコが不自然な動きを感じたことはほとんどなかった。それ以上に、呼ぶと曲がり角から顔だけ覗かせたり、顔を擦り寄せてきたり、柵を隔てて走り回る僕(少年)をみたりする仕草ひとつひとつがトリコをただのNPCではない一匹の獣であると感じさせてくれた。だから移動に多少時間がかかっていても、僕はまったく気にならなかった。赤ん坊が泣くのと同じで、大きな獣が軽快には動けないことは当然だからだ。
ゲームのNPCに話かける僕
ところどころでトリコにエサを与えるパートがある。エサを与えることでトリコの体力が回復したり、なにか新しいスキルを習得することもなく、この作業がどのようなゲーム的意味を持つのかよくわからなかった(収集要素ではあるらしい)が、この要素の導入は正解だったと思う。これはトリコと僕が絆を深める儀式のようなものだった。トリコは目の前にエサを置けば自分で食べるし、タイミングを合わせれば投げたエサをうまくキャッチする。最初は作業的に与えていたものの、トリコの背中にのったり、助けたり助けられたりする中、うっかりエサ樽をキャッチさせるつもりで投げトリコの顔面にぶつけてしまったとき、思わず「ごめんごめん」と呟いてしまった。ある状況下でエサを与えた際は「頑張れ!」と声をあげてしまった。長くゲームを遊んできて、こんな経験は初めてだった。トリコと僕には絆が生まれていた。
曖昧さの表現、限度はあるけれど、それが生き物
言うことを聞いたり、聞かなかったり
この巨大な生き物にはR1ボタンで指示することができる。場所や物を指差しながらひと声かけるくらいのもので、指示としてはかなり抽象的だ。このアバウトな指示をトリコはうまく解釈したり、してくれなかったりする。「ちがう、そうじゃない」と言いたくなる場面は無数にあったが、そもそも言葉が通じない者同士、指示も理解も完全にはできないことは当然だ。トリコも少年をほったらかして勝手にどこかに行くということもなく(これはゲーム的な都合も関係あるだろう)、基本的には少年の指示を聞いてくれる。つまりトリコにはゲームの邪魔をする悪意がないことがゲームプレイを通じて理解できる。この主人公を助ける機能としての側面と、意志ある生き物としての側面の間を行き来する曖昧さが、他のゲームNPCと一線を画している。ザキとザラキを連発するアイツとは決定的に違う点だ。
主体性と相棒感
さらにトリコはこちらの指示を受けるだけでなく、自分で考えて行動しているらしいことが分かる。プレイヤーがトリコの背中に乗ると自分で進むべき道を判断し進んでくれることがある。(もちろん毎回ではない)うまく自分の思惑とトリコの行動が合致すると連帯感が生まれる。限られたコミュニケーション手段しかない本作ではなおさらだ。オンラインFPSなどでチャットもなくお互い向かい合って屈伸しまくったときの感覚にも似ている。なんだか「通じ合った」気がするのだ。
プレイヤーが感情を載せてしまえば勝利
とはいえ、ドライに言えばトリコはただのゲームのキャラクターだし誰かが操作しているわけでもなくコンピューターが作り出した01の集合体だ(目も80年代SF映画のコンピュータのような光方をするし)。一般にAIに感情が宿る可能性について僕は何も言えないが、少なくとも現状では感情を持ったゲームキャラクターは存在しない。でも世の中にはロボット犬AIBOやファミレスの配膳ロボットを愛でる人たちがいるように、接する人間側の感情を載せてしまったらその時点で勝利だと思う。ドラクエ5でパパスがやられて眉ひとつ動かさなかった冷血人間の僕でも、満身創痍のトリコを見ているのは心が落ち着かなかった。
トリコは決して快適なサポートをしてくれる存在ではないし、時にイライラさせられることもあるけれど、その不便さも含めてトリコだと受け止められるように仕上がっている点でトリコを生き物として描く試みは大成功だと思っている。
愛しくないので許せないイライラ
あまりに問題の多いカメラと操作性
鈍重なカメラと狭い地形に翻弄される
本作のカメラにはとにかく難点が目立つ。重くゆったり加速するように動く本作のカメラは、美しく重厚な本作の雰囲気とマッチしているし、カメラ酔いを防ぐ効果もあるだろう。しかし、カメラとして求められる機能が果たされていない。見たい方向がみえない。たとえば開けた空間に出たとき、トリコは最終目的地(と思われる)の方向を気にして見上げるような姿勢をとる。僕も併せてその方向がみたいのにカメラが上方向に上がりきらない。目標物が見切れてしまい非常にモヤモヤするし、せっかくの美しい風景に浸ることも難しい。またカメラは地形に影響されて勝手に動く。狭い空間にトリコといるときなど最悪で、視点が暴れて雰囲気をぶち壊すし、暴れたカメラがリセットされる瞬間、場面転換と誤解するような暗転処理が入る。何かイベントが始まったのかと勘違いさせるのは演出としてもNGだ。
ところどころシビアなアクション
本作はアクションゲームとしてできることは少ない。少年は直接的な攻撃手段を持たず、敵の出現にはトリコが対応する、どちらかと言えばアドベンチャーゲームだと思うが、時々妙にシビアな操作を求められる。足場をジャンプして渡るシーンがとくに顕著だが、足場に手が届かず落下する場面が頻発した。足場や崖の突起に手がちゃんと届いていないと当たり前のように落下死する。これがゼルダの伝説ならアクションゲームとして理解できるが、アドベンチャーゲームにジャンプアクションは求めていない。だいたいの方向が合っていればゲーム側でサポートして足場を渡らせるべきだ。オートセーブなので極端に巻き戻しを食らうことはないが、そもそも少年もトリコも快適な操作感とは程遠いため、少しのやり直しでも感じるフラストレーションは大きかった。
微妙なヒントと学習ステップ
ナレーションによるヒント提示
謎解きに詰まり同じ場所にとどまっていると、未来の少年(おじさん)が過去を回想する形でナレーションが入りヒントをくれる。これは一見助け舟のようだが実際は違う。僕の察しが悪いのは本人が一番自覚しているので言わないで。
ヒントになってないのよ
ある場面で詰まったとき、ナレーションで「大鷲の身体を使って脱出した」というヒントが再生された。しかし肝心の大鷲は少年の頭上の木製天井の上を歩いており、指示しても何も起こらない。結局「トリコを歩き回らせて木製床を崩してできた隙間から、トリコが垂らした尻尾をよじ登る」が正解だったのだが、これを「大鷲の身体を使え」でどうにかさせるのは難しいだろう。本作の謎解きはたいてい「大鷲の身体を使う」だし、ひとつの謎解きであってもいくつか手順を経る必要がある場合、どこで詰まってしまうかは人それぞれだ。そこに画一的なヒントを出したところで解決にはつながらない。
それ先に言って
また、ある場面で詰まった僕は最終的に攻略サイトをみてしまった箇所がある。水面そばにある足場に登りたいが設置されていたハシゴは壊れていた、僕は何度かジャンプしたり周りを見渡してハシゴの代わりになるものを探したが見つからなかった。ならばここは段差を登る場面でなく、他の方向から来たときの帰り道になるのかと解釈して一旦諦めた。その場は他にも順路っぽいところがいくつかあったからだ。でも実際は段差を登るのが正解で、トリコに水面にダイブさせ起こした波を利用して段差をよじ登るという荒業で通ることが正解だった。たしかに段差の近くに行くと何も指示しなくてもトリコはダイブをかましてきていたと後になって気づくが、上述のカメラワークの悪さと、何より「トリコが水にダイブして起こした波を利用する」という学習ステップがそれ以前になく(なかったよね?)その発想はみじんも浮かばなかった。ここに限ってヒントナレーションのおっさんもダンマリだったのが憎らしい。
多くを語らない世界で語っちゃうナンセンス
上田作品はプレイヤーの考察余地が大きいスタイルだ。異文明で、社会から切り離された場所で、話し相手がおらず孤独で、補完するドキュメントもなく、セリフも少ない。限られた情報しか得ることはできず、そこが上田作品の魅力と見ている人も多いかもしれない。できるだけ情報を語らないように努めている作品で、言葉でヒントを提供する方法は矛盾を感じる。ヒントの上手い下手は無関係にあまり上手なやり方ではないと思う。とはいえ他のやりようを思いつくわけではないのだけれど。
僕を惑わせたインタラクション環境
『トリコ』は正解ルートを探すゲーム
本作は『アンチャーテッド』シリーズや『トゥームレイダー』シリーズのように、ある程度開けた空間の中で、壁をよじ登ったり、水を泳いだり、隣の建物へ飛び移ったり、時には仕掛けを解くなどして正解のルートを探すゲームだ。この手のゲームに特徴的なのはUIだ。特にナビゲーションに関わるサポートは限定的であることが多く、プレイヤーは常に周囲の地形を観察して、インタラクションできるか考えることを求められる。このエリアのゴールはどこで、そこに行くための経路として、あそこは「行ける」ここは「行けない」と直感的にプレイヤーに理解させることが大事だ。
登る意味のないところに登れるツタ
残念ながら『トリコ』はこの点も上手ではなかった。行く必要のないところにも行けてしまうのだ。一例だがよじ登ることができるツタが攻略上必要のない場所にも設置されている。攻略に行き詰まったときに出会うと最悪で、総当たりを試す状況の中では、下手にインタラクションできるものがあることで、見落としを疑ってしまい余計な時間を過ごしてしまった。背景としてもツタを設置したいのであれば、色なり種類を変える等やりようはあったはずだ。行けるところと行けないところがしっかり区別管理がされていない。余計な時間をかけさせられるのもまたイライラする要因だった。
冗長な展開
一般的には短いがこのゲームでは長すぎるプレイ時間
本作はクリアタイムが明確に示されないので具体的なクリアタイムがわからないが、クリア時獲得したトロフィーで15時間未満であることはわかった。体感で言えば10~13時間程度だと思う。アドベンチャーゲームとしては一般的な長さに収まっているが、正直終盤は飽きてしまった。
変化に乏しく冗長な展開
相棒と協力するパートはまだまだ続けたい気持ちはあったけれど、それ以外の仕掛けやアクションパートはゲーム全体で変化に乏しく、シチュエーションも最初から最後まで空が見えるか見えないか程度の違いで印象をがらっと変えるものはなかった。ところどころある少年の窮地を救うトリコのシネマティックシーンの迫力は素晴らしいだけに全体の冗長さが残念だ。アクションパートをもっとコンパクトにまとめてトリコとの関わりを中心にし、数時間で終わるボリュームだったら、(プレイ時間が短いことに賛否は起こるだろうが)少なくとも僕の評価はもっと高かったと思う。
まとめ
- トリコはかわいい、かわいいは正義
- トリコへの愛を台無しにするフラストレーションなゲームプレイ
- 思いのほか冗長なゲーム展開